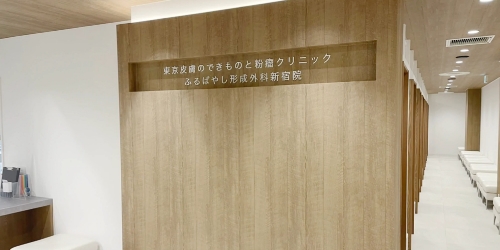目次
気になるほくろを「自分で取ってしまいたい」と思ったことはないでしょうか。しかし、自己判断の除去には、感染症・傷跡・悪性腫瘍の見落としなど、重大なリスクが潜んでいます。
本記事では、ほくろのセルフ除去が危険な理由や、安全な治療方法、日常生活で行える予防法について解説します。大切な肌と健康を守るために、正しい知識を身につけましょう。
自分でほくろを除去するのは危険
一見すると単なる「ほくろ」でも、自己判断で除去を試みることは危険です。市販の除去クリームやハサミなどを使用して無理に取り除こうとすると、感染症のリスクや傷跡が残る可能性があります。
さらに、悪性腫瘍だった場合は命にかかわる重大な事態に発展するおそれがあるため注意が必要です。
自分でほくろを除去するリスク
自分でほくろを除去するリスクは以下のとおりです。
感染症の危険性
無菌状態ではない環境や、消毒されていない器具を使用してほくろを除去すると、傷口から細菌が侵入し感染症を引き起こすおそれがあります。
腫れや赤み、激しい痛み、発熱などを伴うこともあり、日常生活に支障をきたすほど悪化する可能性も少なくありません。自分でほくろを除去すると、ほくろの除去とは無関係な追加の治療や抗生物質の投与などが必要になることがあり、かえって身体的・経済的な負担が増加してしまいます。
安易な自己処理は、結果的に美容目的の逆効果となることもあるため注意が必要です。
傷跡や色素沈着が残る可能性
自己処理によって皮膚に強いダメージを与えると、傷跡が残ったり色素沈着を引き起こしたりするケースがあります。とくに、無理に削ったり切ったりした場合、皮膚の深い層まで損傷を受けやすく、修復までに時間がかかるだけでなく、完全にもとの状態に戻らないこともあります。
結果的にもとのほくろよりも目立つ跡になってしまうこともあり、見た目の悩みが悪化する可能性もあるでしょう。ほくろの除去をする際は、必ず医療機関で適切な処置を受けることが重要です。
悪性腫瘍(がん)の見落とし
自己判断でほくろを除去する最大のリスクは、悪性腫瘍(皮膚がん)を見落とす可能性です。見た目だけでは、良性か悪性かを見分けることは困難です。
悪性だった場合、自己処理によって病変を取り除くと発見が遅れ、適切な治療を受けられないまま命にかかわる事態に発展する可能性もあります。
「ただのほくろ」と判断せず、専門医による診断を受けることが安全かつ確実な対処法と言えるでしょう。
ネットで噂のセルフ除去方法は本当に安全?
ネットで噂のセルフ除去方法は本当に安全なのかどうか、詳しく解説します。
ほくろ除去クリーム・もぐさ
「塗るだけでほくろが取れる」と謳う除去クリームや、もぐさを使用した治療方法は肌への刺激が強く、火傷のリスクが伴います。一時的にほくろが消えたように見えることもありますが、以下のような深刻な副作用を起こすリスクがあります。
- 薬の強い刺激による炎症や化膿
- 色素沈着やクレーターのような傷跡が残る
- ほくろの根元(深部)が残り再発するリスク
「簡単・安価・手軽」などの言葉に惑わされず、専門の医療機関で診断を受けることが安全な選択です。
針やハサミで切り取る
針やハサミなどの器具を使って自分でほくろを除去することも、非常に危険です。器具の消毒が不十分であれば細菌感染のリスクが高まり、切除の深さを誤ると過剰な出血や皮膚組織の損傷を引き起こすおそれがあります。
思っている以上に出血することも多く、止血がうまくできないと傷口が広がり感染を助長する原因にもなりかねません。深く切り込み過ぎると、傷跡が陥没したりケロイド(盛り上がった瘢痕)になったりすることもあります。
また、自己処理による切除は痛みを伴います。たとえ小さなほくろであっても、針やハサミを使用して取り除くことは極めてリスクが高いことを認識しておきましょう。
市販除去グッズの効果は?
ほくろ除去用のペンやパッチなど、市販の除去グッズが一部で流通していますが、効果は個人差が大きく、医学的な根拠が不十分な製品も少なくありません。日本皮膚科学会などの専門機関も、市販グッズによるセルフ除去は推奨していません。
また、インターネットで手に入る輸入品の中には、日本国内では認可されていない成分が含まれていることもあります。肌トラブルや健康被害を引き起こすリスクもあるため、安易な宣伝に惑わされないよう注意しましょう。
良性・悪性ほくろの見分け方
良性・悪性ほくろの見分け方として、皮膚がんの診断に用いられる以下の「ABCDEルール」が有効です。
| ABCDEルール | 補足 |
|---|---|
| Asymmetry(左右非対称) | ほくろの形が左右対称ではない |
| Border(境界が不明瞭) | 周囲がぼやけていたり、ギザギザしている |
| Color(色が不均一) | 黒・茶色・赤・青など、複数の色が混在している |
| Diameter(直径が6mm以上) | 大きさが拡大している |
| Evolution(進行性の変化) | 短期間でかゆみ・出血・色・形などの変化が見られる |
上記の項目に一つでも当てはまる場合は、自己判断せずに医師の診察を受けることが推奨されます。
医療機関でのほくろの除去方法
皮膚科や美容外科など、専門の医療機関では安全かつ適切な方法でほくろの除去が行われます。主な治療方法は以下のとおりです。
レーザー治療
レーザー治療は、炭酸ガスレーザーなどを用いて、ほくろの色素細胞(メラノサイト)を焼き切る方法です。主に良性と診断された小さなほくろに用いられることが多くあります。
施術時間が短く、出血もほとんどありません。メスを使用しないため傷跡が目立ちにくく、ダウンタイムも短い傾向にあります。
ただし、皮膚の深部に根がある場合は再発のリスクもあるため、医師による適切な診断と施術が重要です。また、悪性の疑いがあるほくろには適用されません。
くり抜き法
くり抜き法は、専用の小さな円形メスを使用し、ほくろを皮膚の深部ごとくり抜く方法です。ほくろの根までしっかり取り除けるため、再発リスクが低いのが特徴です。
ほくろの大きさにもよりますが、縫合が不要なケースもあるため傷跡も比較的小さく済みます。ただし、ほくろのサイズや位置によっては縫合が必要になる場合もあるため、医師の判断が重要です。
電気焼灼
電気焼灼は、高周波電流でほくろを焼き取る方法です。同時に止血もできるため、出血を最小限に抑えられることが特徴です。
施術時間が短くリスクも少ない方法ですが、術後は赤みや色素沈着が出る可能性があります。できるだけ跡を残さないためには、医師の技術と適切なアフターケアが必要です。
切除術
切除術は、メスを使用してほくろを皮膚ごと切り取り、縫合する外科的手術です。大きなほくろや悪性の疑いのあるほくろにも対応できます。
切除した組織を病理検査に回せるため、正確な診断が行えるのが大きなメリットです。縫合が必要なため跡は残りやすいものの、安全性と確実性が高く、再発リスクも少ない治療方法です。
ほくろを増やさないための対策
ほくろを自分で取ることは推奨されませんが、日常生活でほくろが増えるリスクを低下させることができます。具体的には、以下のような対策を心がけましょう。
紫外線予防を徹底する
ほくろを増やさないためには、紫外線予防を徹底することが重要です。UV(紫外線)は、皮膚のメラニン生成を促進するためです。
外出時には日焼け止めを塗り、帽子や日傘を使用するなど、紫外線対策を心がけましょう。紫外線対策を行うことで、肌へのダメージを軽減し、ほくろの増加や術後の色素沈着を予防できます。
物理的な肌への刺激を減らす
物理的な肌への刺激を減らすことも、ほくろの増加を予防するのに効果的です。肌への摩擦や刺激が、ほくろの増加や悪化の原因になることがあるためです。肌への刺激を減らすポイントは以下のとおりです。
- やわらかく肌触りの良い素材の衣類を選ぶ
- きつすぎる服やアクセサリーを避ける
- ほくろをできるだけ触らないようにする
日常的に配慮することで、ほくろへの刺激を低減できます。
ほくろ除去ならふるばやし形成外科へご相談ください
気になるほくろを「自分で取りたい」と思うことがあるかもしれませんが、自己処理は非常に危険です。感染症や傷跡のリスク、悪性腫瘍の発見が遅れてしまうなど、重大な健康被害につながる可能性も少なくありません。
ほくろの除去は、必ず専門の医療機関で診断を受けたうえで適切な処置を行うことが重要です。大切な肌と命を守るためにも、自己判断ではなく医師に相談しましょう。
院長紹介

日本形成外科学会 専門医
古林 玄
私は大阪医科大学を卒業後、大阪医科大学附属病院、市立奈良病院を経て東京へ行き、がん研有明病院、聖路加国際病院で形成外科の専門医として様々な手術の経験を積んできました。
がん研有明病院では再建症例を中心に形成外科分野の治療を行い、乳房再建および整形外科分野の再建を中心に手術を行ってきました。聖路加国際病院では整容的な面から顔面領域の形態手術、また、先天性疾患、手の外科、全身の再建手術に携わって参りました。
この経験を活かし、全身における腫瘍切除を形成外科的に適切な切除を目指し、傷跡の目立たない治療を提供できればと考えております。
他にも多数の症例を解説しています