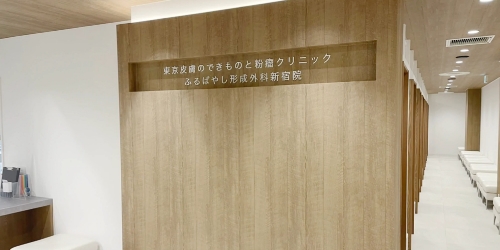目次
顔や体にあるほくろが気になっており、きれいに取り除きたいと考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、「どの治療方法を選べばよいのか分からない」「傷跡は残らない?」など、治療に対して不安を抱えている方も少なくないでしょう。
この記事では、レーザー治療・切除手術・焼灼手術の治療法の違いや施術の流れ、アフターケアまで分かりやすく解説します。さらに、悪性のほくろの見分け方やよくある質問についても紹介します。安心して治療に臨むために、ぜひ参考にしてください。
ほくろ除去治療とは?
ほくろ除去治療とは、皮膚上にできた「ほくろ(色素性母斑)」を取り除く施術のことです。
そもそもほくろは、以下のような要因で発生します。
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| メラニン色素の増加 | メラノサイト(色素細胞)が増殖することで発生する |
| 遺伝的要因 | 家族にほくろが多い人がいる場合、できやすい傾向がある |
| 紫外線(UV) | 紫外線によるダメージがメラノサイトを刺激し、ほくろの発生を促す可能性がある |
| ホルモンの影響 | 思春期や妊娠などでホルモンバランスが変化すると、ほくろが増えることがある |
| 加齢 | 年齢を重ねると皮膚の細胞に変化が起き、ほくろが発生することがある |
ほくろは、「見た目が気になる」など美容上の理由で除去する場合と、悪性腫瘍などの可能性を考慮して除去する場合があります。
目的によって、治療方法や保険の適用範囲が異なります。美容目的の場合は自由診療、悪性腫瘍などで治療が目的の場合は保険適用されるケースが一般的です。
ほくろ治療の種類
ほくろの治療は、大きく分けると以下の3つの方法があります。
- レーザー治療
- 切除術
- 焼灼手術
ほくろの除去術とは何か、それぞれの治療内容や違いを詳しく解説します。
レーザー治療
レーザー治療は、炭酸ガスレーザーやYAGレーザーなどを用いて、ほくろの細胞を蒸散・破壊する方法です。小さいほくろの治療に適しています。切らずに除去できるため、傷跡が小さく済むことがメリットです。
局所麻酔を行いレーザーを照射しますが、施術は数分程度で完了します。術後のダウンタイムも短い傾向にあります。
切除手術
メスを使ってほくろを切除し、皮膚を縫い合わせる方法です。5mm以上の大きめのほくろや、悪性の疑いがある場合に適応されます。
病理検査も同時に行えるため、医学的な管理が必要なケースに適しています。術後は抜糸する必要があるため、通院が必要です。
焼灼手術
電気メスや高周波機器などを使用して、ほくろを焼き取る方法です。出血が少なく、処置が短時間で済むことがメリットです。
ただし、深く削りすぎると周りの組織を傷つけてしまい、傷跡が目立ちやすくなります。そのため、医師の技術が重視される治療方法です。
それぞれの治療方法の違い
それぞれの治療方法の違いは、以下のとおりです。
| 治療法 | 除去方法 | 適応サイズ | 特徴 | 治療期間 |
|---|---|---|---|---|
| 切除法 | メスで切る | 中~大 | ・再発しにくい ・病理検査も可能 | 約1~2週間 |
| レーザー | 光で焼灼・蒸散 | 小 | ・傷跡が少ない ・美容目的 | 数日~1週間 |
| 焼灼手術 | 電気で焼灼 | 小~中 | ・傷跡が少ない ・医師の技術が重要 | 約1週間 |
ほくろの大きさや症状によって適切な治療方法があるため、必ず医師と相談の上治療を決めるようにしましょう。
治療の流れ
ほくろの治療の流れは、以下のとおりです。
- 診察、カウンセリング
- 施術
- 術後のケア
それぞれ詳しく見てみましょう。
STEP1診察・カウンセリング
まずは、診察とカウンセリングを行います。所要時間は、20分程度です。ダーモスコピーという特殊カメラでほくろを確認し、良性か悪性かを判断します。
良性の場合は、すぐに施術できるケースがほとんどです。悪性の場合は、後日改めて切除・検査を行います。症状によっては、大学病院を紹介するケースもあります。
STEP2施術
施術をする際は、局所麻酔を使用します。レーザー治療なら数分程度、切除手術や焼灼手術の場合は10~30分程度です。麻酔を使用するため、施術中の痛みはほとんどありません。
STEP3術後のケア
施術後は、肌色の保護テープを3日~1週間程度貼る必要があります。保護テープは、細菌感染の予防と乾燥防止に役立ちます。個人差がありますが、完全に治るまでは1週間程度必要です。
治療後のケアの仕方
治療後、あとが残らないケアの仕方を紹介します。
①紫外線対策をしっかりする
術後の肌は非常にデリケートな状態になっているため、紫外線対策をしっかり行いましょう。日焼けをすると、色素沈着を引き起こす可能性があるためです。
色素沈着を防ぐために、日焼け止めや帽子などのアイテムでUV対策を行ってください。日焼け止めは、敏感肌用の低刺激のものがおすすめです。
②かさぶたを無理に剥がさない
施術した箇所がかさぶたになる可能性がありますが、無理に剝がさないようにしましょう。かさぶたは、自然に剥がれるまで待つことが重要です。無理にはがすと、色素沈着や傷跡が残る原因になります。
③擦ったり、摩擦などの刺激を与えない
患部を強く洗ったり擦ったりして、摩擦などの刺激を与えないようにしましょう。治療後は、肌バリアの機能が低下しており非常に敏感になっています。敏感肌でない場合でも、入浴やスキンケアをする際は、患部を優しく扱いましょう。
そもそもほくろとは
ほくろとは、皮膚の中にあるメラニン色素を作る細胞が集まってできた皮膚腫瘍のことです。大きく分けると、良性と悪性があり、悪性の場合は取り除かなければなりません。
良性のほくろで、日常生活に支障がなく見た目が気にならない場合は、無理に治療する必要はありません。
ただし悪性の場合は、早急に治療する必要があります。
悪性のほくろは、早期発見と適切な治療が重要です。
良性・悪性のほくろの代表例は、以下のとおりです。
- 【良性】ミーシャー母斑
- 【良性】ウンナ母斑
- 【良性】クラーク母斑
- 【良性】スピッツ母斑
- 【悪性】悪性黒色腫(メラノーマ)
- 【悪性】基底細胞癌
それぞれの症状を見てみましょう。
【良性】ミーシャー母斑
- 色:黒色・茶色
- 形:平坦
- 大きさ:通常1cm程度
- 好発部位:顔・首・背中・胸など
【良性】ウンナ母斑
- 色:褐色・赤色
- 形:でこぼこした形
- 大きさ:直径1cm程度
- 好発部位:顔・首・上腕・太ももなど
【良性】クラーク母斑
- 色:茶色・黒色
- 形:平坦
- 大きさ:直径1cm以下
- 好発部位:手のひら、足の裏などを含めた全身
【良性】スピッツ母斑
- 色:黒褐色・赤褐色・淡褐色
- 形:ドーム状に盛り上がることが多い
- 大きさ:6mm以下
- 好発部位:顔や四肢を含めた全身
【悪性】悪性黒色腫(メラノーマ)
- 色:黒や深紅色など、均一ではない
- 形:左右非対称でギザギザしている
- 大きさ:直径6mm以上
- 好発部位:手足の爪や足の裏など
【悪性】基底細胞癌
- 色:肌色・黒色
- 形:小さな盛り上がり
- 大きさ:数mm~数cm(徐々に拡大)
- 好発部位:顔面(鼻や耳の後ろに好発する)
性のほくろとその見分け方
悪性のほくろの判断基準として、ABCDE基準があります。以下のような異変がないかチェックしましょう。
- A:Asymmetry — ほくろの形が左右非対称
- B:Border irregularity — 皮膚とほくろの境界線が不明瞭
- C:Color variegation — ほくろの濃淡が不均一でまだら
- D:Diameter — ほくろの大きさが6mm以上
- E:Evolution — 急速に増大する、形状や色が変化する
上記のような特徴が見られる場合は、皮膚科で「ダーモスコピー検査」を受けましょう。
ダーモスコピー検査は、皮膚科専門医のみが行えるもので、良性・悪性の判断に役立ちます。当院ではダーモスコピー検査で良性か、悪性かのチェックを行っております。気になった方はお気軽にご相談ください。
よくある質問
ほくろは一回で除去できますか?
ほくろの色味の深さや状態によっては、2~3回程度施術が必要になる場合があります。特に深く根のあるほくろは、一度にすべてを取り切ると傷跡が目立ちやすくなる可能性があります。そのため、段階的に治療するケースも珍しくありません。
自力で取ってもいいでしょうか?
自分で無理に除去すると、感染症や深い傷跡、色素沈着が残るリスクがあります。医療機関で適切な処置を受けることをおすすめします。
傷跡は残りますか?
治療方法や個人の体質によって異なりますが、施術後しばらく傷跡が赤くなります。多くは3ヶ月程度で落ち着きますが、肌になじむまでは半年以上かかる場合もあります。
特に直径5mm以上のほくろや皮膚がよく動く箇所の治療をした場合、目立たなくなるまで時間がかかる傾向にあります。術後は処方された軟膏を塗り、患部が乾燥しないようにしましょう。傷跡が赤いうちは紫外線予防をすることで、色素沈着が抑えられます。
ダウンタイム中のメイク・入浴は?
患部を避ければ、当日から洗顔・入浴・メイクが可能です。患部を擦ると、ダウンタイムが長くなり色素沈着が残る可能性も高くなるため、強い摩擦を与えないよう注意してください。
保険適用になるケースは?
悪性を疑われ、病理検査を行う場合は保険適用になることがあります。一方、良性と診断され美容目的で治療する場合は自由診療です。保険適用となるかどうかは医師の判断によって変わるため、詳しくは診察時に相談してください。
ほくろの除去は当院にご相談ください
ほくろの診療で何より大切なことは患者様からお伺いする症状や状況です。そのため、当院ではじっくりと患者様からお話をお伺いし、そのうえで綺麗な仕上がりになるよう患者様の症状や状況に合わせ、適切な治療法をご提案します。
少しでもほくろの除去について気になっている方はお気軽にご相談ください。
院長紹介

日本形成外科学会 専門医
古林 玄
私は大阪医科大学を卒業後、大阪医科大学附属病院、市立奈良病院を経て東京へ行き、がん研有明病院、聖路加国際病院で形成外科の専門医として様々な手術の経験を積んできました。
がん研有明病院では再建症例を中心に形成外科分野の治療を行い、乳房再建および整形外科分野の再建を中心に手術を行ってきました。聖路加国際病院では整容的な面から顔面領域の形態手術、また、先天性疾患、手の外科、全身の再建手術に携わって参りました。
この経験を活かし、全身における腫瘍切除を形成外科的に適切な切除を目指し、傷跡の目立たない治療を提供できればと考えております。
他にも多数の症例を解説しています