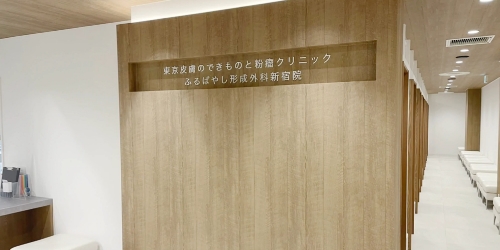脂漏性角化症(しろうせいかくかしょう)は、加齢に伴い現れる良性の皮膚腫瘍で、茶色や黒っぽい色が特徴です。痛みやかゆみもなく放置されがちなイボですが、見た目が気になってレーザー治療を検討する方は少なくありません。
本記事では、脂漏性角化症(別名:老人性イボ)をレーザーで治療する方法や効果、料金などを解説します。
脂漏性角化症(しろうせいかくかしょう)とは?
最初に、脂漏性角化症(しろうせいかくかしょう)について「症状」「原因」に分けて解説します。
症状
脂漏性角化症(しろうせいかくかしょう)は、40歳以降の方にできやすい皮膚の良性腫瘍です。30代から出現する方もいらっしゃいますが、比較的年齢層が高い方にできやすい傾向があります。脂漏性角化症は、一般的なイボとは異なり、ウイルスが原因ではないため、人に感染することはありません。
色は茶色や黒っぽい色で、少し表面が盛り上がった形状が特徴です。通常は痛みやかゆみがなく、放置している方も多いです。しかし、見た目を気にして「目立つ場所にできた」「だんだん大きくなってきた」などお悩みを抱える方は治療を検討する方もいらっしゃいます。脂漏性角化症は、悪性化することはないですが、自然に消えることもありません。
原因
脂漏性角化症のはっきりとした原因はまだ解明されていませんが、メラニンの蓄積が影響していると考えられています。
特に顔や手、足のシミは、長い月日をかけて紫外線を浴びることで、皮膚の細胞に異常を引き起こすことが要因とされています。その他にも、遺伝やホルモンバランスなども原因の一つと考えられていますが、老人性イボと呼ばれるだけあって加齢が最も多い原因だとされています。
脂漏性角化症にはレーザー治療が効果的
脂漏性角化症の治療には主に、脂漏性角化症には2種類のレーザー機器が用いられています。それぞれのレーザーについては、後述します。
脂漏性角化症にはレーザー治療が効果的で、手術と比べて出血が少なく、治療後の回復が早いのが特徴の治療方法です。特に「きれいに治したい方」や「何度も通うのが難しい方」におすすめです。レーザー治療では、特定の波長を持つレーザー光を皮膚に照射し、脂漏性角化症の原因となる細胞のみを破壊します。そのため早い効果と確実な効果を得られる治療法として、幅広いシミ治療に使われてきました。レーザー治療は、脂漏性角化症だけでなく赤あざや青あざなど、他の皮膚疾患にも幅広く使用されています。
そして、治療後の回復期間が短いため、数日から数週間で日常生活に戻ることが可能です。しかし、治療後の肌は敏感な状態になっているので、日焼け止めの使用や紫外線対策を行いましょう。そうすることで、色素沈着や炎症を予防できます。このように、レーザー治療は「早い回復」かつ「きれいな仕上がり」ができるため、効果的な治療法と言えます。
炭酸ガスレーザーについて
1つ目は、レーザー治療の一つである「炭酸ガスレーザー」について紹介します。
期待できる効果と治療回数
炭酸ガスレーザーは、水分に吸収されやすい特性があり、皮膚に照射すると一瞬で熱エネルギーに変換され、組織を蒸散させます。治療ではこの特性を活かし、脂漏性角化症だけでなく、ほくろやイボの除去にも幅広く利用されてきました。施術するときは局所麻酔を使用するため痛みに弱い人も心配ありません。また、メスが必要な手術よりも傷が浅く出血量も少ないため、皮膚へのダメージが少ないことも特徴です。
基本的には1回の治療で除去が可能ですが、大きさや数に応じて2~3回の治療が必要となることもあります。その時は、施術間隔を1~1.5か月ほど空けて再度照射することが多いです。治療の回数や間隔は状態によっても異なるため、早く治したいという気持ちを抑えて、医師と相談しながら慎重に進めることが大切です。
料金
炭酸ガスレーザーの料金相場については、一般的に3,000円~10,000円程度となっており、脂漏性角化症の大きさによって異なります。そしてこの治療については、保険が適用されない自費治療となるため、クリニックによって差があります。また、イボが発生した部位や大きさによって費用も異なります。詳細な料金が気になる方は、事前にお問い合わせください。
リスクと注意点
炭酸ガスレーザー治療はメリットが多い治療法ですが、いくつかのリスクや注意点があります。まず、施術後に赤みが続くことがあります。通常3~4か月で落ち着く方が多いですが、赤い盛り上がりやくぼみなどができてしまう恐れがあります。特に、深く削りすぎると傷跡が残るリスクが高まるため、施術する部位や照射範囲によっては傷跡が目立ってしまう恐れがあります。
また、施術後は皮膚が敏感になりやすく、テーピングや紫外線対策を1~2週間程度行う必要があります。人によっては、色素沈着や傷跡が残り、複数回の治療が必要な場合もあります。そして、妊娠中や疾患のある方、ケロイド体質の方などは施術ができないケースもあるため、医師と相談することが重要です。
実績が豊富な医療機関を選び、リスクと注意点を十分に理解した上で治療を受けるようにしましょう。
Qスイッチレーザーについて
Qスイッチレーザーは特に、濃い色のシミに高い効果を発揮するレーザーです。茶色や黒っぽい脂漏性角化症の治療によく用いられるレーザー治療です。
期待できる効果と治療回数
Qスイッチレーザーはシミやそばかす、あざの治療によく用いられる治療法です。特に、Qスイッチアレキサンドライトレーザーは、皮膚表面から深層にわたるメラニンをピンポイントで改善できます。この特性により、茶色や黒色のシミ、脂漏性角化症などの治療に幅広く使われています。
治療回数は症状の深さや濃さによって異なりますが、一般的に1~3回の施術で改善する場合が多いです。複数回に渡る場合は、数か月間隔を空けて照射を繰り返すことで徐々に治療を行っていきます。
そして短時間のレーザー照射により、熱の影響を最小限に抑えられるため、周囲の正常組織へのダメージが少ないのも特徴です。しかし炭酸ガスレーザーに比べて、即効性には劣る場合があるため、治療プランについては医師と相談して決めることが大切です。
料金
Qスイッチレーザーの料金は、治療する脂漏性角化症の大きさや個数に応じて異なります。
5㎜以下などの比較的小さい場合は4,000円程度が相場です。ただし、クリニックによって大きさの範囲や個数によって料金が設定されていることがほとんどです。Qスイッチレーザーについても保険適用外となりますので、あらかじめ料金について問い合わせしましょう。
リスクと注意点
Qスイッチレーザーのリスクと注意点としては、まず赤みが2~3か月続くことがあり、体質によってはさらに長期間赤みが残る場合があります。この赤みが治まらない限り、追加照射を行うことはできませんが、経過とともに多くの方は赤みが減少してくのでご安心ください。
また、最も注意が必要なリスクとして炎症後色素沈着(PIH)が挙げられます。治療後の皮膚がレーザーの熱エネルギーによって刺激を受け、シミのように見える色素沈着を起こすことがあります。この現象は再発したように誤解される方も多く、再照射を希望されることも多いです。しかし追加照射はさらに色素沈着を悪化させる恐れがあるため、医師と相談しましょう。
さらに、治療後は肌が敏感な状態になるため、日焼け止めを使用し紫外線を避けることが重要です。かさぶたができている間は、軟膏を塗布し、保護することで早期改善が見込めます。特に紫外線を浴びるとシミが再発しやすいため、できれば日差しの弱い季節に治療を行うと安心です。
まとめ
脂漏性角化症は、皮膚の老化による良性の腫瘍で、通常は痛みや悪性の心配はほとんどありません。しかし、見た目が気になる場合には治療を検討する方も多いです。その中でも、当院が採用するQスイッチレーザー治療は、皮膚を削らずにメラニン色素にのみ反応するため、正常な皮膚へのダメージを最小限に抑えた治療が可能です。
また、跡が残りにくく短期間での回復が期待されるため、脂漏性角化症の治療に適しています。当院は、皮膚の治療を専門に扱う形成外科専門医が在籍しているクリニックです。再発や傷跡が目立ちにくい治療を提案しておりますので、ぜひご相談ください。
関連記事
院長紹介

日本形成外科学会 専門医
古林 玄
私は大阪医科大学を卒業後、大阪医科大学附属病院、市立奈良病院を経て東京へ行き、がん研有明病院、聖路加国際病院で形成外科の専門医として様々な手術の経験を積んできました。
がん研有明病院では再建症例を中心に形成外科分野の治療を行い、乳房再建および整形外科分野の再建を中心に手術を行ってきました。聖路加国際病院では整容的な面から顔面領域の形態手術、また、先天性疾患、手の外科、全身の再建手術に携わって参りました。
この経験を活かし、全身における腫瘍切除を形成外科的に適切な切除を目指し、傷跡の目立たない治療を提供できればと考えております。